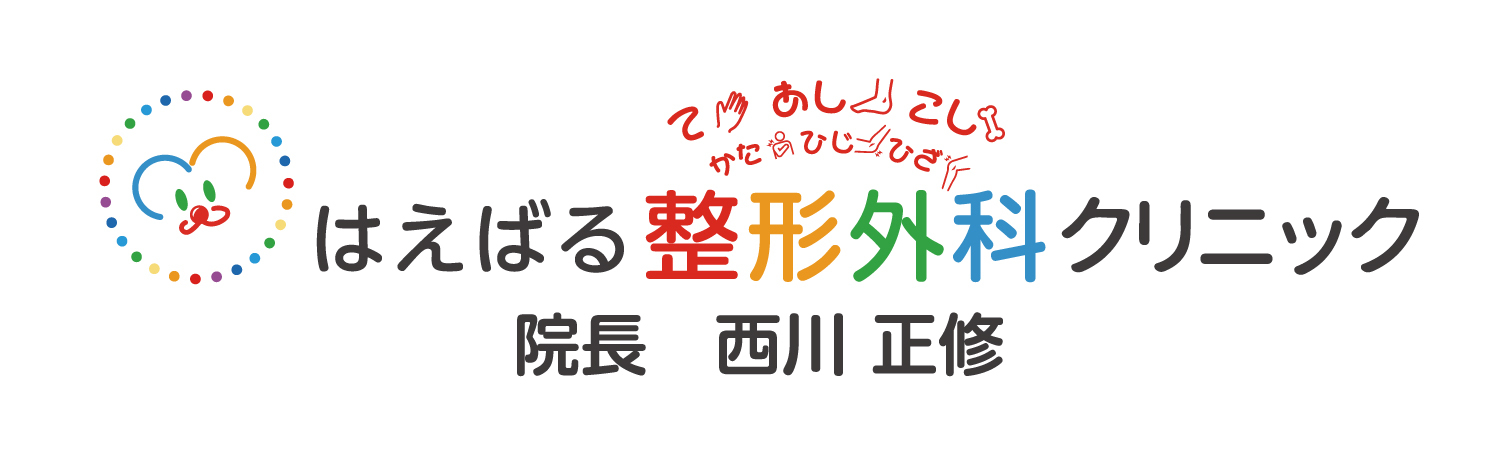耳鼻咽喉科
耳の疾患
中耳炎

中耳炎は、もっとも代表的な耳の疾患のうちのひとつです。耳の奥には鼓膜があり、そのすぐ内側に「中耳」と呼ばれる部分があります。
この中耳で炎症が起こる病気を「中耳炎」といいます。小さなお子さまに多い「急性中耳炎」がよく知られていますが、そのほかにも「滲出性中耳炎」「慢性中耳炎」「好酸球性中耳炎」など、さまざまな種類があります。
急性中耳炎

「急性中耳炎」とは、文字通り「急に起こる中耳の炎症」です。体のつくりがまだ未発達な小さなお子さまに多く見られる病気で、風邪を引いた後に続いて発症することもよくあります。
発熱とともに耳の奥が痛み、鼓膜自体にも炎症が起こるため腫れが生じます。また、鼓膜の奥(中耳)に膿が溜まると、鼓膜がうまく振動できず、音を正しく伝えることができなくなります。
その結果、耳栓をしたような聞こえにくさを感じることがあり、これを「伝音難聴」と呼びます。
治療
急性中耳炎の治療では、原因となる細菌感染を取り除くことが重要です。そのため、鼻や副鼻腔、咽頭などの炎症を同時に治療し、抗生剤で治療を進めます。
子どもの急性中耳炎は再発を繰り返すことも多く、症状によっては抗生剤の治療が長引く場合もあります。また、急性中耳炎の多くは、鼻から耳管を通じて感染が広がるため、鼻の処置やネブライザーによる鼻・上咽頭の炎症改善も大切です。
耳鳴り

実際には音がしていないのに、「ジー」「ピー」「キーン」などの音が自分の耳や頭の中で雑音が聞こえる状態を言います。
人によって音の種類や大きさはさまざまで、片耳だけの場合もあれば両耳に感じることもあります。
気圧の変化などで一時的に生じる耳鳴りは誰にでも起こるもので、通常は心配いりませんが、症状が長引いたり、日常生活に支障をきたすような場合には、治療が必要となります。
耳鳴りの原因はさまざまで、加齢や騒音の影響、筋肉の痙攣、病気などのほか、ストレス・疲労・睡眠不足がきっかけとなることもあります。
音が持続する場合もあれば、消えたと思うと再び現れる場合もあり、症状の現れ方は人によって異なります。
治療
耳鳴りは「音の病気」ではなく、耳や脳が音の信号を正しく処理できなくなっている状態です。原因によって治療法が異なるため、まずは聴力検査や必要に応じてMRI検査などを行い、原因を特定します。
治療は主に薬物療法によって経過を観察していきますが、耳鳴りの症状が完全に消えない場合もあります。
難聴

様々な要因により音が聴き取りにくくなる、またはまったく聞こえなくなる状態のことを言います。ご高齢の方だけでなく、若い方にも起こりうる病気です。
難聴を放置すると、聴力が完全に戻らなくなる可能性が高くなるため、異変を感じたらできるだけ早めに受診し、適切な治療を受けることが大切です。
特に突発性難聴は、症状が現れてから48時間以内に治療を開始することが、聴力回復の重要なポイントとなります。
治療によっても聞こえが完全に回復しない場合や、加齢による難聴など治療が難しい場合でも、補聴器を使用して聞こえを補うことで生活の質の改善が期待できます。
治療
突発性難聴にはステロイド、ビタミン剤、血液循環を促進する薬など薬物療法が一般的です。
治療は、開始が早ければ早いほど、聴力改善の可能性が高く、遅くとも発症1週間以内の受診が望まれます。
鼻の疾患
副鼻腔炎

副鼻腔炎とは、風邪などで粘り気のある鼻水や鼻づまりが生じ、副鼻腔に膿がたまる病気です。
主な症状としては、においを感じにくい、歯の痛み、頭痛、おでこや頬の痛みなどがあります。
副鼻腔炎の原因として、カビや細菌などが挙げられます。なお、アレルギー性鼻炎の場合は、花粉やダニなどによって引き起こされることが多いといえます。
症状の経過によって分類され、急性の症状は「急性副鼻腔炎」3か月以上続く場合は「慢性副鼻腔炎(蓄膿症)」と呼ばれます。
急性副鼻腔炎
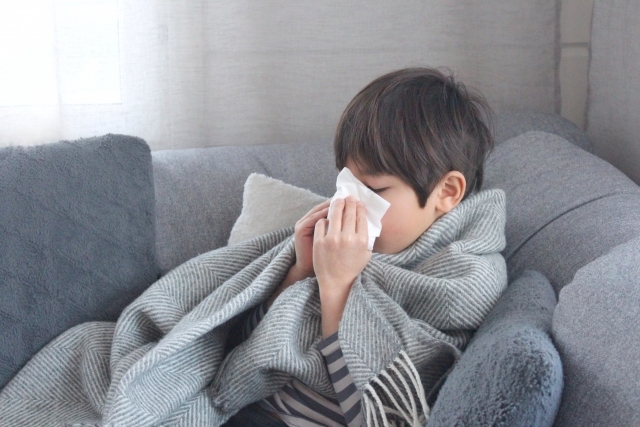
急性副鼻腔炎は、風邪と勘違いされることもあり、放置すると治りにくくなる場合があります。
多くは、風邪のウイルス感染のあとに続く細菌感染が原因です。鼻腔の粘膜が炎症で腫れると、鼻水や鼻づまりだけでなく、顔の腫れ、目や頬が押されるような感覚、痛みなどの症状が現れることもあります。
発症のきっかけはアレルギー性鼻炎や風邪であることが多く、通常は1か月ほどで自然に改善するケースが多いです。
治療
急性副鼻腔炎の治療には、抗菌薬を使用します。また、症状に応じて鼻処置(鼻汁吸引・自然口開大処置など)、排膿処置(手術等の外科処置)が行われる場合もあります。
抗菌薬投与に関しては、軽症の場合は抗菌薬なしで経過観察をすることも多いですが、中等症以上の急性副鼻腔炎、あるいは慢性副鼻腔炎の急性増悪に関しては抗菌薬の内服が推奨されております。
アレルギー性鼻炎

アレルギー反応によって鼻の粘膜が炎症を起こすことで、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状が現れる病気です。アレルギー反応とは、本来は害のない物質(アレルゲン)に対して、体が異物と誤認し、免疫系が過剰に反応することで引き起こされます。
また、症状が起こる時期によって「通年性」と「季節性」の2種類に分けられます。
通年性アレルギー性鼻炎は、年間を通して症状が現れるタイプで、主な原因はハウスダストです。特にダニが多く、猫や犬などのペットも原因となることがあります。
季節性アレルギー性鼻炎は、特定の季節に症状が現れるタイプで、ほとんどの場合はスギやヒノキ、ブタクサなどの花粉が原因です。
治療
アレルギー性鼻炎には、主に2つの治療法があります。
- 薬物療法(対症療法)
くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を和らげたり抑えたりする治療です。症状が出たときに使うことで、日常生活を快適に過ごせるようにします。
- アレルゲン免疫療法(根本治療)
アレルギーそのものに働きかける治療で、原因物質(アレルゲン)に対する体質改善が期待できます。
また、日常生活でのアレルゲンの除去や回避も症状の改善に有効です。
特に鼻から入るアレルゲンの量を減らすことは、治療の第一歩となります。
喉の疾患
扁桃炎

咽頭(のど)にはリンパ組織が集まった扁桃があります。
扁桃には、上咽頭にある咽頭扁桃(アデノイド)、口を開けたときに左右に見える口蓋扁桃、舌の付け根にある舌根扁桃の3つがあります。
一般的に「扁桃炎」と呼ばれるのは、口蓋扁桃の炎症を指します。
扁桃炎には、ウイルスや細菌の感染によって急に起こる急性扁桃炎と、炎症が慢性的に続く慢性扁桃炎があります。
急性扁桃炎

急性扁桃炎は、細菌やウイルスによる急激な感染が原因で扁桃に炎症が起こる病気です。
典型的な症状としては、高熱や強い喉の痛み、扁桃の腫れや白い膿の付着が見られ、全身の倦怠感や頭痛を伴うこともあります。
扁桃炎の原因となる病原体で注意が必要なのが「溶連菌」です。
主に保菌者の咳・くしゃみなどに含まれる菌を吸い込むことで感染します。
早めに治療を開始し、最後まで治療をすることが大切です。
治療
急性扁桃炎は薬物療法を行います。「非ステロイド性消炎鎮痛薬」や、「抗菌薬」で喉の腫れを抑え改善するため治療を行います。
呼吸や食事に支障をきたす場合には、入院して抗生物質の点滴をすることもあります。また、年間に何回も扁桃炎を繰り返す方には、全身麻酔を行い両側の口蓋扁桃を摘出する手術が推奨されることがあります。
急性咽頭炎

急性咽頭炎とは、喉の粘膜やリンパ組織に起こる急性の炎症です。
ウイルスまたは細菌の感染を原因としますので、咳、くしゃみ、接触などによって人にうつることがあります。
初めはウイルス感染だけでも、後から細菌感染を伴うこともありますし、最初から細菌感染が起こる場合もあります。
近年では、PM2.5や黄砂などの環境要因が咽頭炎の発症に影響を与えることもあります。
治療
急性咽頭炎は、薬物療法によって治療を行います。
ウイルス感染が原因の場合、ウイルスそのものを治す特効薬はないため、のどの炎症を抑える薬で症状を和らげます。細菌感染が原因の場合には、抗生剤による治療が行われます。